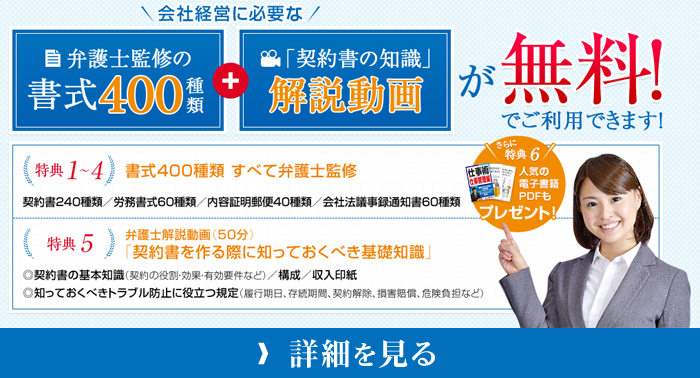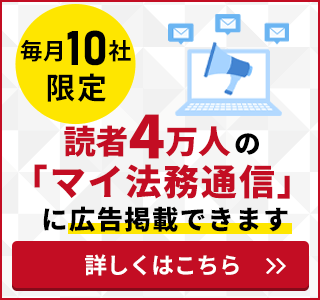会社法議事録・通知書のテンプレートが無料


マイ法務とは

顧問弁護士を雇えない中小企業経営者や個人事業主の方にも、
ビジネスに必要な契約書の書式ひな形や経営で知っておくべき法律情報や動画解説をご提供。
法務書式はすべて弁護士が監修しています。
主に以下のコンテンツを無料でご利用いただけます。

弁護士が監修した書式・ひな形400種類を無料ダウンロードできます。
会社法通知書・議事録・契約書・労務書式・内容証明郵便の書式など
以下より、ご希望の書式を検索できます。


新着記事

企業の経理担当者が知っておくべき税務申告の種類と申告・納期限

税務会計と財務会計の違い。法人税の申告手続きをする際の注意点

法人が納める主な税金と種類ごとの納付期限を解説
書式集カテゴリー一覧
会社法務書式
内容証明郵便
- クーリングオフ
- 不動産の修繕
- 不動産売買
- 不動産関連
- 交通事故
- 人事労務
- 会社法
- 債務不履行請求
- 債権債務に関する契約
- 商品売買
- 委任契約
- 慰謝料
- 知的財産権に関する契約
- 解雇
- 請負に関する契約
- 賃貸借契約
- 過払金返還
- 金銭の貸借契約
労務書式
契約書書式
- コンサルティング契約
- サービスの提供に関する契約
- ビジネスに関する契約書
- 不動産の売買契約
- 交換に関する契約
- 任意後見に関する契約
- 使用契約
- 使用貸借契約
- 信託契約
- 入場に関する契約
- 共同経営
- 利用に関する契約
- 労働災害
- 動産の売買契約
- 受託契約
- 和解に関する契約
- 商品・物品・製品の売買
- 商品券等に関する契約
- 土地に関する契約
- 委任契約
- 寄託契約
- 工事契約
- 年少者との契約
- 抵当権に関する契約
- 担保・保証に関する契約
- 更新に関する契約
- 清掃に関する契約
- 相殺に関する契約
- 相続・贈与関係の書式
- 看板の仕様に関する契約
- 示談書
- 組合契約
- 経営に関する契約
- 結婚・離婚に関する契約
- 船舶に関する契約
- 製造に関する契約
- 調査に関する契約
- 請負契約
- 賃貸借契約
- 賃貸借契約(借地・借家)
- 賃貸借契約(動産)
- 賃貸借契約(商品)
- 賃貸借契約(土地)
- 賃貸借契約(建物)
- 質権に関する契約
- 運送に関する契約
- 金銭の貸借契約
会計事務所の実務に役立つ情報
- 税理士法人から独立した税理士が税理士法人の顧客を引き抜きした事例
- 贈与税を必要経費に算入できるのか?
- 記帳代行業務の業務委託契約書のひな形
- 税理士に対する損害賠償請求(税賠)を防止する方法
- 税理士顧問契約書のひな形25種類以上(税理士会で配っている契約書とは異なります)
トラブル防止のために契約書のリーガルチェックが必要な理由
契約をする際、通常は契約書を交わします。
たとえば、ある会社で契約書を作成した場合、「法的な不備はないか」、「自社にとって不利となる条件が書かれていないか」ということは非常に重要になります。
こうしたチェックを法律の専門家にしてもらうことを「リーガルチェック」といいます。
経営者や総務・法務部などの担当者にとっては、トラブルを未然に防ぎ、自社の利益を守るためには必須の業務です。
そこで今回は、契約と契約書について、基礎知識から作成の際の注意ポイントまでを法的な立場から、わかりやすく解説します。
「目次」
・契約とは?
・契約自由の原則とは?
・自由にできない契約とは?
・契約の拘束力を有効にするための要件とは?
・契約当事者に関する有効要件とは?
・契約書の役割とは?
・契約書を構成する7つの項目をチェック
・印紙を貼らないとペナルティを課されることもある
・トラブル防止&自社に有利な契約書作成のための13の規定
・署名・捺印していない人には契約書の拘束力は発揮されない
・会社の代表者は個人としての債務は負わない
・契約における署名捺印の注意ポイントとは?
・署名、記名、押印の違いとは?
・まとめ
契約とは?
契約とは、専門的に言うと、「2人以上の当事者同士の合意に基づいて権利義務関係を発生させる法律行為」となります。
たとえば、土地の売買を例に考えてみると、Aさんが「土地を売ります」と言ったことに対して、Bさんが「土地を買います」と言えば、両者の間に合意によって契約が成立するわけです。
そして、そこには「売る義務」、「買う義務」、「お金を払う義務」が発生します。
契約自由の原則とは?
契約には、「私的自治の原則」といって、契約を当事者の自由に任せて、国家はこれに干渉してはならない、という原則があります。
これを「契約自由の原則」ともいうのですが、次の3つの自由があります。
1.相手方選択の自由
たとえば土地を売却する時に、Aさんに売ってもいいし、Bさんに売ってもいいし、Cさんに売ってもいいという自由があります。
「誰に売りなさい」ということは強制されない、という自由です。
2.内容決定の自由
土地を売却する時に、「金額はいくらにしますか」、「引き渡しの日はいつにしますか」、あるいは「土地を売る前に測量をしますか」というように、お互いが合意をすれば内容は自由に決定することができます。
これを、内容決定の自由といいます。
3.方式の自由
契約を交わす場合は契約書を作ることが一般的ですが、口頭で決めてもいいし、書面化してもいいし、どういう方式で決めてもいいとされています。
これを、方式の自由といいます。
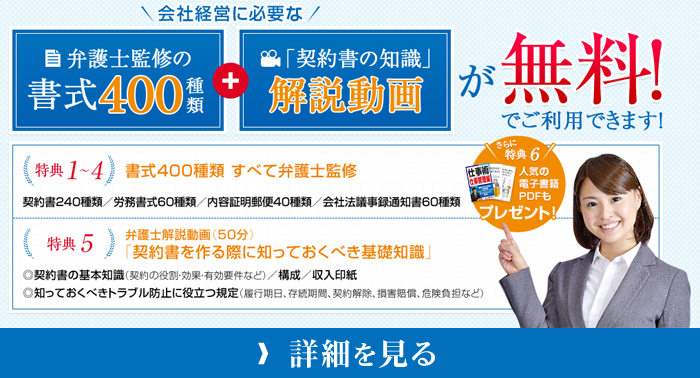
自由にできない契約とは?
契約には3つの自由があるとはいっても、「公序良俗に反する契約」や「強行法規に違反する内容の契約」は無効ということになっています。
たとえば、「覚醒剤を売ります」、「買います」だとか、「愛人になりますか」、「なります」というような契約は公序良俗に違反しているので、いくら契約書を作っても法的には無効になります。
強行法規の例としては、労働基準法があります。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えた場合は、残業代(割増賃金)を支払わなければいけないと規定しています。
仮に、従業員として入社する際、「私はいくら働いても一切、残業代はもらいません」と誓約書を書いて会社と合意したとしても、これは無効になります。
「内容決定の自由があるではないですか!」と言っても、強行法規として労働基準法に違反する合意はすべて無効ということになるので注意が必要です。
契約の拘束力を有効にするための要件とは?
契約が成立した後で、相手が約束を破る場合があります。
そうした場合、ペナルティを定めることによって約束を守ってもらうようにするという工夫が必要になります
たとえば、土地の売買で考えてみます。
AさんとBさんが土地の売買契約をして、AさんがBさんに土地を売却することにしました。
ところが、契約を履行する前にAさんはCさんに土地を売って登記を移してしまいました。
こうした場合は当然、「契約違反ではないか!」ということになるでしょう。
そこで前もって契約書に、契約違反に対する罰則、たとえば解除条項とか損害賠償条項を定めることで契約の相手を拘束しておく必要があります。
ただし、契約に拘束力を持たせることが有効となるためには、いくつかの要件が必要になります。
1.確定性
内容が確定していなければなりません。
たとえば、AさんがBさんに「土地を売ります」と言っても、どの土地なのかわからないというのでは契約が確定されません。
「○○番地の土地、広さ40平米」といったように、契約書に特定する必要があるのです。
2.実現可能性
契約の内容は実現できるものでなければなりません。
たとえば、AさんがBさんに建物を売却するという契約をしたにもかかわらず、契約の前にこの建物が地震で壊れていたというような場合、この契約は実現不可能であり、仮に新しい建物を建てても、それは別のものということになるので、実現不可能となってしまいます。
3.適法性
たとえば、前述の覚せい剤の契約のように違法なものではなく、適法でなければいけません。
4.社会的妥当性
適法性と同じようなものですが、たとえば会社の機密資料を盗んで持ってきてもらう契約などは、社会的に見て明らかに不相当で妥当性はないので無効となります。
契約当事者に関する有効要件とは?
契約の拘束力を有効にするためには、契約の内容だけでなく、契約当事者に関する有効要件というものもあります。
1.当事者に意思能力が存在していること
自分は何の契約をするのか、何をいくらで買うのか、ということが理解できていなければ契約は無効ということになります。
たとえば3歳児が、「この土地が欲しいから5000万円で買う」と言ったとしても、判断の意思能力がないので契約は無効になります。
2.当事者に行為能力が存在していること
これは法律行為をする能力のことです。
たとえば、未成年者が「土地を買います」と言って実際にお金を払ったとしても、後でこの法律行為を取り消すことができます。
なぜなら、未成年者には行為能力がないとされているからです。
ちなみに、未成年者が契約をする時には、行為能力がある親などの親権者が同意をしなければ後で取り消すことができます。
3.意思の欠缺(けんけつ)・瑕疵(かし)が存在しないこと
たとえば、「とても価値がある土地だ」とだまされて山林を買わされた詐欺のような場合や、包丁で脅されて土地の売買の判子を押してしまったというように、意思に欠缺(欠けていることや不十分なこと)や、瑕疵(欠点や過失)がある場合、あるいは正しい意思に基づいていない場合は契約が無効になったり取り消されたりすることになります。
4.代理権・代表権があること
会社の場合、契約書の契約者名には「代表取締役」と書いて代表印を押しますが、通常の商取引については社員が現場の実務をしているでしょう。
しかし、社員が実務のやり取りをして判子を押す場合、その社員に代理権がないと契約は無効になってしまいます。
厳密にいうと、代理権がなかったとしても、「表見代理(ひょうけんだいり)」といって本人に効果が帰属するようなケースがありますが、原則として代理権や代表権がない場合、契約は有効には成立しないということになります。
そのため、代表権限があることをきちんと登記で確認したり、あるいはそうでない社員や第三者の場合は、会社が判子を押した委任状を持ってきてもらうということで、代理権・代表権を確認するということになります。
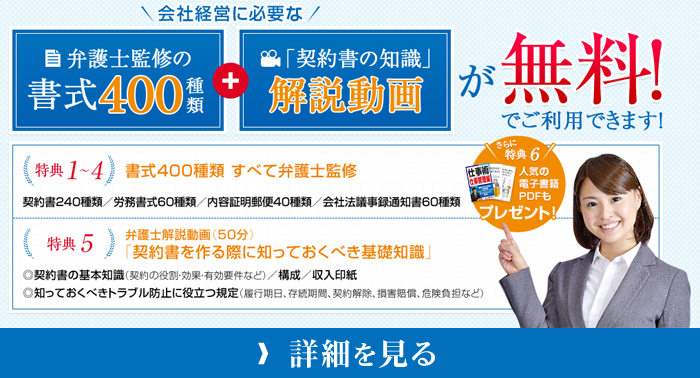
契約書の役割とは?
1.契約当事者の備忘のため
契約を結ぶまでには、さまざまな話し合いがあると思います。
ところが人間が行なうことですから、一つひとつ内容を取り決めたとしても、後で忘れてしまうことがあるでしょう。
そのため、契約当事者が忘れないように、きちんと書面にしておくというのが契約書の役割のひとつになります。
2.紛争が起きた場合に備える
契約書は、きちんとお互いが納得しあって署名・捺印したものですから、「この内容で取り決めました」という強力な証拠になります。
そのため、後で紛争が起きた時に裁判所に契約書を提出すれば、「どういう内容・条件の約束だったのか」という強力な証拠になります。
契約書を作っておくと、仮にトラブルが起きた場合、「あなたが約束を守らなかったのだから損害賠償をすべきではないか」というように相手に主張することができます。
一瞬で終わるような契約であれば契約書は必要なでしょう。
しかし、土地の売買や会社がサービスを提供する際のサービス提供契約、あるいは会社のホームページ制作の契約書など、取り決めが多岐に及ぶような契約の場合には、きちんと契約書を結んでおくことが大切になるのです。
契約書を構成する7つの項目をチェック
契約書は、ほぼ決まった項目で構成されています。
ここでは、その中から主な7つの構成項目について解説します。
①タイトル
「売買契約書」、「請負契約書」、「ホームページ製作契約書」といったように契約書にはタイトルが入ります。
中には「合意書」や「覚書」、「協定書」といったタイトルになることがありますが、法的な効力に変わりはないと覚えておいてください。
ただし、「仮契約書」などの場合は仮に作ってあるので、それが本当に有効なのか、確定的に効力が発生するのか、ということについては内容を注意深く読む必要があります。
②前文
前文とは、「この契約はこのような契約です」ということを最初に説明している文章です。
③契約の内容(条・項・号)
簡単な契約の場合は、契約書が1枚というものもありますが、複雑なものの場合は数百ページにも及ぶことがあります。
そうした場合、「第〇条 〇項 〇号」というように記述します。
④後文
契約書の一番最後に、「この契約はこういう内容です」というような文言が入りますが、これを後文といいます。
⑤作成年月日
⑥当事者の表示
誰と誰が契約しました、というように当事者名を記入します。
⑦目録
必要な場合に記入します。
たとえば、土地の売買ではどの土地かを確定しなければならないので、最後に土地目録というものを作って「○○町○番○番地 ○平米」というような記載をしておきます。
具体例
ここでは、「不動産の売買契約書」を例に具体的に見ていきましょう。
------------------------------------
(売主)●●(以下「甲」という。)と、(買主)●●(以下「乙」という。)は、別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)につき、以下のとおり、売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、本件不動産を以下の条件で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けた。
第2条(義務)
1 乙は、甲に対し、以下の義務を負う。
① 乙は、平成26年1月31日までに、本件不動産を株式会社●●から買い受ける。
② ・・・・・・
------------------------------------
①タイトルは「売買契約書」です。
これが、「売買合意書」であっても法的には有効ということになります。
②が前文です。
「(売主)○○(以下「甲」という。)」と「(買主)○○(以下「乙」という。)」は、別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)につき、以下のとおり、売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。」
この契約は何について取り決めているものなのか、ということを一番初めに明らかにすると同時に、「甲」、「乙」、「本件不動産」といった略語をここで取り決めてしまおうという役割もあります。
③で内容に入っていきます。
「第1条(目的) 甲は、乙に対し、本件不動産を以下の条件で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けた。」
契約書というのは、「甲」と「乙」の合意ですから、甲と乙が何を合意したのかということを「第○条」というように取り決めておくことになっています。
④は後文です。
すべての条文が終わったら、最後に記載します。
「本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、各一通を保有することとする。」
以上をもってすべて合意しました、ということです。
「その証拠として契約書を2通作りました、だから1通だけではなく2通ありますよ」ということが、ここでわかります。
契約書を相互に持ち合うということです。
これは、一方だけが契約書を持っていると、片方に対して「契約書を見せてくれ」と言っても、「嫌だ」と言われたら契約書の内容がわからないので、「お互いに1通ずつ持ちましょう」ということになっているわけです。
⑤は日付です。
日付が空欄の契約書をたまに見ますが、その場合、いつ合意がされたのかがわからず裁判で争いになる可能性があります。
裁判になった場合、ある出来事が「あった前なのか」、あるいは「後なのか」という部分が重要になります。
そのため、契約書を作成した時には必ず日付を漏らさず書いておくということが必要になってきます。
できれば、本当に合意した日を書くのが正しい記載の仕方です。
バックデートして、「半年前に契約したことにしましょう」といって契約書を作る場合がありますが、そうすると本当に記載した時がいつなのかがわからなくなってしまうからです。
バックデートする場合には、条文の内容に、「この内容は○月○日からの甲乙間の取引に適用されるものとすることを合意した」ということを記載しておけばよいのであって、わざわざ日付の記載にバックデートする必要はないのです。
⑥は当事者の表示です。
甲乙それぞれに住所・氏名・押印をします。
印鑑がないと、「私は約束していない」と言われてトラブルの元になる可能性もあるので、必ず双方が署名・捺印するということが必要です。
⑦不動産の場合などでは物件目録がつきます
物件目録をつけて、「どこの土地なのか」ということを特定する、ということになります。
これをしっかりやっていないと、「どこの土地なのかわからない」、あるいは「何平米なのか?」といった部分で、お互いに違うことを主張し出すことがあり得ますので、きちんと物件目録に目を通して、登記簿謄本と間違いがないかどうかを確認するということも大切です。
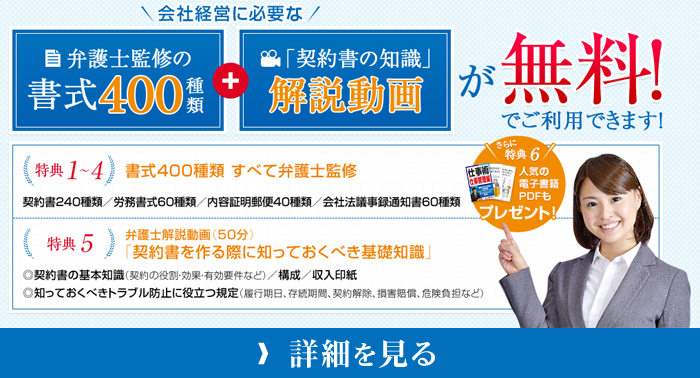
印紙を貼らないとペナルティを課されることもある
「印紙税法」の定めによって、「不動産譲渡に関する契約書」や、「金銭消費貸借契約書」などを作成する場合には収入印紙を貼付し、消印を押す必要があります。
複数の契約書を作成する場合には、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要となります。
なお、収入印紙が貼っていなくても、じつは契約の効力には影響がありません。
しかし、契約書を交わす際には、国税庁のホームページや印紙税法の書籍などを参考に、自分が行なう契約では印紙が必要なのかどうか、きちんと調べて印紙をしっかり貼るのがよいでしょう。
消印を押すというのは、二度と使えないようにすることですから、印紙を貼ったら印紙と契約書の間に判子を押したり、ペンで線を引いて使えないようにするなど方法で消印をするということが必要です。
契約書を2通作った場合、それぞれに印紙を貼って、印紙の費用は折半するというのが一般的だと思いますが、これは法的な規定ではないので、もちろんどちらか一方が印紙代を負担してもいいですし、お互いでどのように取り決めてもいいものです。
ただし、契約書に印紙を貼っていないと、税務調査の際にペナルティがあるので注意が必要です。
トラブル防止&自社に有利な契約書作成のための13の規定
契約書を取り交わす際、トラブル防止に役立つ基本的な条項について解説をしていきます。
①履行期日
たとえば、「甲は乙に対し、令和○年○月○日までに、本件土地を現状有姿のまま引き渡す」というように、いつ契約を履行するかを、しっかり明記することが大切です。
履行期日を決めずに、「この土地を売ります」、「買います」、「値段は〇〇万円です」とだけ決めておくと、後々「いつお金を払うのか?」、「いつ土地を引き渡すのか?」、「いつ登記をすればいいのか?」という問題が発生します。
また、買い手が支払いをズルズルと伸ばしても、「支払期限は決めていなかったではないか」と言われてしまうかもしれません。
必ず、「甲はいつまでに何をする」、「乙はいつまでに何をする」ということを取り決めておくことが必要です。
②存続期間
「本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする」、あるいは、「本契約の期間は、令和○年○月○日から○年間とする」というように存続期間をきちんと明記します。
「賃貸借契約」や「ビル管理契約」など、ある程度一定の期間ずっと契約が続くという場合には、「いつまでその契約が続くのか」について必ず定めておかなければなりません。
それを怠ると、契約をいつ終わらせればいいのかわかりませんし、いつまで継続すればいいのかわかりません。
そうすると、金銭的には、「いつまでの契約の分が、いくらの金額なのか」がわからないということになってきます。
また、「○月○日までとする」というように期日が決まっているなら、その後の契約の取り決めもしておかなければいけません。
「更新するのか、しないのか」、「更新するには何か手続きが必要なのか」、あるいは「自動的に更新するのか」、といったことを決めておく必要があります。
③契約解除条項
「甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。」
このような条項を入れておき、本契約のうち、ひとつでも違反した場合には契約を解除できるという規定を設けておきます。
ただし法的には、こうした規定条項がなくても、民法第541条「履行遅滞等による解除権」の規定により契約を解除することができます。
たとえば、AさんがBさんに土地を売却するという契約をして、Bさんは1月1日までに5000万円支払わなければならなかったところ、いざ1月1日になっても支払いがないとします。
そこで、AさんがBさんに「5000万円払ってください」と言ったにもかかわらず払ってくれない場合、催告の後、ある程度の期間が経過すれば契約を解除することができます。
そうでないと、土地の売却代金を支払ってもらえないままその契約に一生拘束されることになってしまうからです。
一方、民法の規定では契約解除できない場合もあります。
たとえば、監督官庁から営業停止を受けた時など、「信用を失うような行為」があった時です。
しかし、上記のような規定条項を設定しておけば、相手に「信用を失った行為」があった場合にはすぐに解除できて、他の人と契約をし直すことができるのでトラブル防止になります。
④期限の利益喪失条項
たとえば、次のような条項を設定しておきます。
「甲が以下の各号のいずれかに該当した場合、甲は当然に本契約及びその他乙との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点において甲が負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならない。」
これはどういうことかというと、たとえば、AさんがBさんに土地を売却するとします。
Bさんは、「一括では支払えません」と言って、金額5000万円を500万円の10回払いにする場合、この分割払いを「期限の利益」といいます。
なぜなら、Bさんにとっては利益があるからです。
ただし、Bさんが1月に500万円、2月に500万円を支払ったが、3月、4月には支払っていないという場合、AさんはせっかくBさんのために分割払いにしてあげたのに、「これではもう分割払いは認められない、残金は一括で支払ってくれ」と言いたくなるでしょう。
すると、Bさんは「期限の利益を失う」ことになります。
期限の利益を失うと、分割払いの約束をしていても、AさんはBさんに対して、残金は一括で支払うように言えるようになります。
これが「期限の利益の喪失」です。
そのため、分割払いにするような場合には、必ず「期限の利益の喪失条項」を入れておくのがいいでしょう。
そうしておけば、「本契約の一つにでも違反したとき」、要するに500万の支払いを1回でも怠ったら残額は一括で支払うように言えるからです。
⑤損害賠償
次のような条項を入れておきます。
「甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相手方に対してその損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。」
損害賠償については、契約書に規定していなくても損害を与えられた場合は、民法の規定によって相手方に損害賠償請求ができます。
しかし、商取引で債務不履行があり裁判を起こす場合、その弁護士費用は各自で負担しなければいけません。
そこで、上記のような弁護士費用についての規定条項を入れておくと、相手に請求することができるのです。
このように、いかに有利に契約書を書いていくかというのが大切になってきます。
⑥違約罰
違約罰については、次のような条項を入れておきます。
「甲又は乙は、解除、解約又は本契約の重大な義務に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相手方に対して代金総額(消費税込)の20%相当額の違約金を賠償しなければならない。ただし、これを超える損害が発生したときは、その超過額も賠償しなければならない。」
たとえば、AさんがBさんに建物を売却する場合に、Bさんが代金をいつまでも支払ってくれないので契約を解除するといった時、本来はAさんに生じた損害がいくらなのかというのを証明しなければいけません。
ところが、上記のような違約罰を定めておくと、損害額を証明しなくても20%相当額の違約金が損害賠償だということを取り決めておくことができるのです。
また、AさんがBさんに土地を売却する契約をした場合で、Bさんが代金を払ってくれないために取引が遅れたことによって、Aさんがどのような損害を被ったのか、どのように証明すればいいでしょうか。
ただ金額の支払いを待っていただけなので、その間に土地の金額が下がったのかどうかを証明することは非常に難しいものです。
そこで、不動産の売買の場合には、大抵10%や20%の違約金を「違約罰」として定めていることが多いのです。
取引において相手が債務不履行の際には、違約罰を定めておくことによって証明の負担を減らせるということになります。
⑦危険負担
建物を売買する際に、たとえば引渡期日が1月1日で、その前の12月に大地震が起きて建物が壊れてしまった、というような場合は建物の引渡ができません。
その時に、「引渡ができないからこの売買はなし」になるのか、あるいは「引渡はできないけれど契約したのだから代金を払う義務がある」のかという問題が生じます。
これが、危険負担の問題です。
危険負担に関しては、次のような条項を入れておきます。
「引渡前に生じた本件物品の滅失、毀損、減量、変質、その他一切の損害は買主の責に帰すべきものを除き売主が負担し、本件物品の引渡後に生じたこれらの損害は、売主の責に帰すべきものを除き買主が負担する。」
これは、万が一の時の規定となります。
⑧担保責任
担保責任については、次のような条項を入れておきます。
「本件物品の引渡後の検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは、引渡時から6か月以内に限り、乙は甲に対して、無償の修理又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。また、当該瑕疵によって契約の目的が達成できない場合には、乙は本契約を解除することができる。」
では、建物を引き渡して、その後にシロアリや雨漏りなどの瑕疵が発見された場合は、どうすればいいのでしょうか。
その場合は、「売買をなしにするのか」、「あるいは修理をするのか」、「いつまでに修理しなければいけないのか」などを、この条項で取り決めておくことになります。
ここでは、「引渡時から6か月以内であれば修理する」、あるいは「代金を減額するが、6か月過ぎた場合は無効である」ということが契約で書かれています。
当然、そうした場合も想定して契約をしなければいけないので、「いつまでの間」、そして「瑕疵が見つかった場合にはどうするのか」ということを契約書で定めておくことが必要になってきます。
⑨保証人
本人が支払わない、または支払えない時には本人に代わって払う義務を負担するのが保証人です。
次のような条項を入れておきます。
「丙は、乙の連帯保証人として、本契約により生じる乙の甲に対する一切の債務の弁済につき、連帯して保証する。」
保証人については、金融機関等でお金を借りる時に、「保証人を誰にしますか」ということで要求されることがあると思います。
そのため、お金を貸す時に、「この人は本当にお金を返してくれるだろうか」というような疑念がある場合、あるいは取引をする場合でも、「この人は信用力がないが…」、「誰か安全な保証人を付けてくれれば取引をしてもいいが…」というような時に保証人を付けることになります。
⑩相殺の予約
これはイレギュラーな場合で、あまり想定できないかもしれませんが、次のような条項を入れておきます。
「甲は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が乙に対して負担する債務と、本契約または本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が乙に対して負担する債務と本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき、甲が乙に対して負担する債権とをその債権債務の期限にかかわらず、いつでもこれを対当額において相殺することができる。」
たとえば、AさんがBさんに土地を売却する契約をして、代金が5000万円の場合、じつは過去にBさんがAさんに5000万円を貸したことがあって、それが返済されていない場合には、AさんとBさんがそれぞれ5000万円の債権を持ち合っていることになります。
そうした場合には、わざわざ5000万円を支払って、同時に5000万円を返済してもらうよりは、「お金の移動はなしにしましょう」としたほうがお互いにラクですから、このような場合には「相殺」といって債権と債権をなくしてしまうことができるのです。
普通の商取引ではあまりありませんが、商品をそれぞれ購入し合っているような場合は、それぞれの商品代金を相殺するという条項を入れる場合があります。
⑪諸費用の負担
次のような条項を入れておきます。
「本契約の締結に要する印紙その他の費用は、甲が負担するものとする。
甲は、引渡期日に、引渡場所に本件物品を持参して引き渡す。なお、引渡しに要する費用は甲の負担とする。」
契約に際しては、「誰が印紙代を負担するのか」、「固定資産税は誰が負担するのか」、「この日までの分は誰が負担するのか」というような問題が出てきます。
あるいは、物を送るような場合には、「誰が送料を負担するのか」、あるいは、「お金を振り込むときの振込手数料を誰が負担するのか」という問題が出てきます。
取引をするには、さまざまな付随費用が掛かってきます。
そのため、上記のようなことを決めておかないとトラブルになる可能性がありますし、そのために契約が成立しないのは、もったいないことです。
ですから、手数料が掛かりそうなものの場合には、諸費用の負担についての条項を入れておくことが必要です。
⑫裁判管轄
裁判管轄については、このような条項を入れておくといいでしょう。
「甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、○○簡易裁判所又は○○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。」
たとえば、AさんがBさんに対して土地を売却する時に、Aさんは東京、Bさんは沖縄にいるとします。
その契約書には、「裁判所は沖縄地方裁判所を専属管轄にします」と書いてあったのですが、Aさんはよく確認せずに判子を押してしまいました。
ところが、Bさんは期日になっても5000万円を払ってこないので、Aさんが東京地裁に裁判を起こそうとしたら、東京地裁は契約書を見て、「これは東京地裁では起こせません。沖縄地裁でやってください」と言われてしまう、というケースがあります。
こうしたトラブルを防ぐために、裁判管轄の条項を定めておきます。
このようなケースでは、Aさんは東京では裁判を起こせずにBさんのいる沖縄まで行って裁判を起こさなければなりません。
となると、東京の弁護士を頼むと、その都度沖縄に行く日当や交通費、場合によっては宿泊費もかかるかもしれません。
裁判は1年や2年はかかるものですから、その間に結構な経費がかかってしまいます。
ところが反対に、この契約書で「東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」となっていたら東京で裁判を起こすことができますし、Bさんが裁判を起こそうとしたら、東京まで行って裁判を起こさなければならなくなります。
ですから、裁判管轄というのは、自分が裁判を起こす時のことを考えて、自分に有利な裁判管轄を決めておくということが必要になってきます。
⑬協議条項
最後は、協議条項です。
「本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。」
何かトラブルがあったら話し合いましょう、ということが書いてあります。
必ずしも法的な効力が生ずる部分ではなくて、「契約する時はお互い仲良くやっていこう」ということなので、それが文言になっていて、一般的にこのような条項が記載されることになっています。
署名・捺印していない人には契約書の拘束力は発揮されない
ここからは、その他の契約の際の注意事項について解説します。
まず、当事者でない者は契約書では拘束できません。
たとえば、甲さんと乙さんが契約書を結びます。
その契約書の中には、次のような条項があったとします。
「乙が債務を履行しない場合には、丙が債務を履行する」
このような条項が入っていて、かつ甲さんと乙さんが判子をすでに押し合っているという状況を考えてみましょう。
実際に契約をして、取引が始まったにもかかわらず、乙さんが債務を履行しない場合、この契約書には「丙が債務を履行する」と書いてあることから、甲さんは丙さんに対して裁判を起こしました。
すると、丙さんは「私はそんな契約書は知りませんよ。私の判子が押されていないでしょ?」と言いました。
そうなると、甲さんは裁判で負けてしまいます。
なぜなら、丙さんはこの契約書の当事者にはなっていないからです。
そのため、誰かに契約書の拘束力を持たせたい場合には、必ずその人の署名・捺印をもらう必要があります。
署名捺印をしていない人の名前が契約書に書いてあったとしても、それには契約の拘束力はないということに注意が必要です。
弁護士ではない、法律の素人の方が作った契約書には、署名・捺印をしていない人の名前が書いてあることがありますが、それは無効になるので気をつけてください。
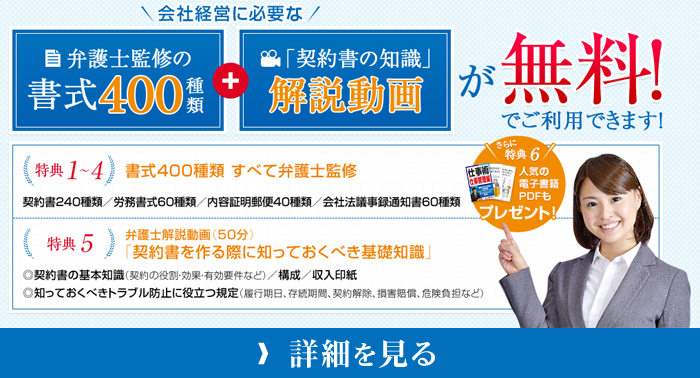
会社の代表者は個人としての債務は負わない
ここに、「みらい株式会社 代表取締役○○」と署名があって、判子が押してある契約書があるとします。
みらい株式会社と取引をしていたところ、お金の支払いが滞っており、関係者から、「どうも会社を閉めたらしい」という話を聞きました。
「じゃあ、社長のところに行って支払ってもらおう」ということで債権者は社長のところに行きました。
ところが社長は、「それは会社で契約したことであって、私個人で契約したものではない。会社のほうに請求してください」と言っています。
こうした場合、債権者は社長に対しては請求できない、ということになります。
なぜなら、契約書には、「みらい株式会社代表取締役○○」と署名されて判子が押されているので、社長は会社の代表者として会社のために判子を押したことになるので、これは会社だけが債務を負うことになるのです。
そのため、社長に個人として債務を負わせるためには、会社の判子をもらった下に、連帯保証人として個人の住所・個人の名前・個人の印鑑をもらっておきます。
そうしないと、契約書では拘束できないということになります。
契約における署名捺印の注意ポイントとは?
個人の場合
個人の場合には、「個人の住所」、「個人の名前」、「個人の印鑑」をもらっておくことが必要です。
たとえば、「土地に関する契約」や「金銭消費貸借」などの大事な契約において、契約書に不動文字、つまりワープロで書いた文字で「甲野太郎」とあり、印鑑も三文判ということになると、後で裁判を起こした時に、「これは私が書いたものではありません。私の判子ではありません」と主張された場合、どうやって証明するのかという問題が起きてきます。
ですから、大事な契約の場合、「契約書には実印で押してもらう」、「自分で署名をしてもらう」、印「鑑証明書をもらっておく」ということをお勧めします。
法人の場合
一方、法人の場合、「みらい株式会社 代表取締役 甲野太郎」と書かれた契約書には、甲野太郎さん個人の責任はありません。
この場合、会社だけが責任を負うということになるので注意が必要です。
なお会社ではなく、社団法人や公益法人や事業協同組合などの場合は、「代表取締役」ではなく、「代表理事 甲野太郎」ということで代表印をもらうということになります。
この場合も甲野太郎さん個人ではなくて、公益社団法人が契約をしたということになります。
未成年の場合
未成年者には行為能力がありません。
つまり、18歳の甲野太郎さんが自分で契約をしても、後でその契約を取り消すことができるということになっています。
しかし、民法では「法定代理人」の同意がある場合には契約できると規定しています。
そのため、未成年者と契約するには、本人の印鑑をもらう他に、通常、親権者は父母になっているので、「甲法定代理人親権者父 甲野一郎」と署名して印鑑を押し、「同母 甲野花子」と署名して印鑑を押します。
このように両方の署名をもらっておく必要があることに注意してください。
安易に年齢確認をせずに契約してしまうと、後で取り消されてしまいます。
特にネット取引の場合には注意が必要だと思います。
代理人の場合
「甲野太郎代理人 山野次郎」と署名があり、印鑑が押されている契約書があるとします。
甲野太郎さんの印鑑がもらえないわけですが、ここで甲野太郎さんの印鑑を山野次郎さんが押す場合があります。
この場合、本当に甲野太郎さんの代理として山野次郎さんが署名捺印しているのかを確認しなければいけません。
そうしないと、甲野太郎さんにこの契約の効果は帰属しないということもあるからです。
従って、甲野太郎さんが自分で署名捺印した山野次郎さん宛ての委任状をもらうという必要があります。
さらに、その委任状が有効なのかどうか、という問題もあります。
甲野太郎さんが自分で署名して、甲野太郎さんの実印を押して、印鑑証明を付けて委任状をもらうことが必要です。
そうすると、山野次郎さんは甲野太郎さんの代理人だということが証明されるので、契約時には山野次郎さんの印鑑だけでいいということになります。
大事な契約書の場合には、後から山野次郎さんが「私は知らない」と言うかもしれないので、山野次郎さんの自署と実印と印鑑証明をもらうことになります。
つまり、この場合は甲野太郎さんと山野次郎さんの両方の印鑑証明が必要になってくるのです。
署名、記名、押印の違いとは?
ところで、「署名」、「記名」、「押印」の違いとは何でしょうか?
「署名」とは、自分で手書きをすることです。
「署名押印」とは、署名した後に印鑑を押すことです。
「記名押印」とは、ワープロで打ったり、あるいは判子を押したり、とにかく名前が記されていればいいというものです。
そして、押印というのは判子を押すことです。
会社同士の場合には記名押印が多いと思いますが、個人の場合にはその意思を確定させるために、できれば署名押印にしたほうがいいでしょう。
まとめ
ここまで、契約についての基礎知識から、トラブル防止や自社に有利な契約書を作成する際の注意事項などについて解説しました。
出所のわからない契約書の雛型をインターネットからコピーしたり、昔の契約書を使用したりする方がいますが、そうした行為はトラブルの原因になります。
また、自社に有利な契約書を作成するには、しっかりとした法律知識と豊富な実務経験を持った弁護士などの専門家でないと、なかなか難しい業務です。
契約書を作成する際は、リーガルチェックを含めて、まずは一度、弁護士に相談することをお勧めします。